子育てにおいて、「どう接すれば子どもが自信を持って育つのか」と悩んでいませんか?
私自身、HSP気質のままとして、子どもとの関わり方に試行錯誤してきました。
この記事では、子どもの自己肯定感を育む「見守る育児」の実践法をお伝えします。
自分を愛して、自分らしく生きる力を育てたい
私は、自分の人生がどこか窮屈だったと感じているからこそ、子どもたちにはのびのびと育ってほしと願っています。
好きなことに夢中になったり、やりたいことにどんどんチャレンジしたり…
そんなふうに”自分らしさ”を大切にしながら
ありのままの自分を愛して生きていって欲しい。
そんな思いを込めて「のびのび育ってほしい」と願っているのです。
ママの“気づき”は、子育ての宝物
子どもたちとの暮らしの中には、たくさんの小さな”気づき”があふれています。
- お着替え、手伝ってほしそうだな
- このままだと、つまずくかも
- またケンカが始まりそう…
そんな日常の中の直感や観察力こそが、ママの大切な”育児の力”。
その気づきを、育児に活かしていきましょう。
気づいても、あえて何もしないという関わり方
気づいたことがあっても、つい手を出したり口を出したくなる。
それは、大切な我が子を守りたい気持ちからくる、当たり前の反応です。
- アドバイスしてあげたほうがいいかな
- 失敗させたくないな
- 怪我しないように止めないと
そう思うのは、愛があるからこそ。
でも、ほんの少し立ち止まって、そっと見守ってみてください。
自分で気づき、考え、選ぶ力が、そこからゆっくり育っていきます。
見守る=そばにいること、いつでも応えられる準備
「見守る」とは、ただ離れてほおっておくことではありません。
いつでも手を差し伸べられるように、心を寄せながらそっとみていること。
子供には、自分で目の前の困難を乗り越える力がちゃんと備わっています。
でも、その前に大人が答えを与えてしまうと、その力を発揮するチャンスを奪ってしまうのです。
「助けて」
「手伝って」
と子どもから声が上がることも、自分なりに困難を乗り越えようとする一歩。
だからこそ、「何があっても助けない」と言うわけではなく
まずはそっと見守って、子供が助けを求めてきた時に答えてあげればいい。
必要とされた時に手を差し伸べる。
それだけで、十分愛は伝わります。
「すごいね!」よりも、「うれしいね!」が心を育てる
もうひとつ、子どもとの関わりの中でとても大切なのが「共感」です。
例えば、子供が絵を描いて、ニコニコしながら
「ママみて〜!上手に描けたの〜!」
と嬉しそうに見せてきたとします。
その時、あなたならどう返しますか?
ある親はこう言います:
「わあ!上手に描けたね〜!○○ちゃんって絵が本当に上手だね!」
別の親はこう返します:
「そっか〜!上手に描けたんだね!嬉しいね〜!」
一見似ているようで、この2つには大きな違いがあります。
最初の言葉は「評価」
子供に”うまい””下手”という価値基準を与えてしまう言葉です。
この関わり方が続くと、子どもは「上手って言われる絵」を描こうとするようになります。
一方で、後者の言葉は「共感」
「上手に描けたんだね」
という言葉で子どもの気持ちを受け止め
「嬉しいね〜」
と感情に寄り添っています。
評価をせず、気持ちに共感することで、子どもは「上手にかけたと自分で思えたことが嬉しい」と感じ
自分の”嬉しい”を軸に絵を描くようになっていきます。
たった一言でも、言葉には大きな力があります。
初めのうちは
「今の言葉、ちょっと評価っぽかったかな」
「今回は共感できたかも」
と自分で気づいていくことで、少しづつ”評価”から”共感”へシフトしていけるはずです。
上の子への共感が、妹や弟へもつながっていく
兄弟や姉妹がいるご家庭では、まずいるご家庭では、まず一番上の子に”共感”することが大切です。
上の子が親から共感される体験を重ねていくことで、自然とその関わり方を、下のきょうだいにも向けるようになります。
「わかるよ」
「そうだったんだね」
と気持ちに寄り添ってもらった経験が、そのまま優しさとして引き継がれていくのです。
こうして家庭の中には、共感の連鎖が生まれます。
評価や比べ合いではなく、お互いのの気持ちを大切にしあえる空間に変わっていくのです。
家庭が”共感される場所”であること。
それが、子供達にとって何よりの安心と信頼の土台になります。
「味方でいること」が、子どもを一番強くする
大人って、つい子どもに「評価」をしてしまいがちですよね。
私自身も、言ったあとで「今の、評価だったな…」と気づいて反省することがあります。
でも、それも無理ないんです。
私たちは、小さい頃から”評価されること”が当たりまえの世界で育ってきたから。
だからこそ、すぐに変わらなくても大丈夫。少しづつでいい。
練習することで、気づきは増えていきます。
そして本当は、子どもを評価するのは、子ども自信だけでいいんです。
親の役割は、”いつもあなたの味方だよ”と伝え続けること。
子どもが自分の気持ちを大切にして、自分らしく生きていけるための、安心の土台になること。
評価じゃなく、信じて寄り添うこと。
それが、子どもの「のびのび生きる力」につながっていくのです。


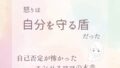
コメント